自社割賦とは?規制やデメリットを分かりやすく解説
金融オンライン

企業が自社の商品やサービスの販売を強化するために、「自社割賦」の導入が注目されています。
しかし、自社割賦を導入するのを難しく感じて、導入に踏み切れない企業が多くあります。
この記事では、自社割賦を導入するメリットやデメリット、包括信用購入あっせんとの違いなどを解説します。

この記事は20年以上金融サービスを提供してきたソモ㈱が執筆しています。

目次
自社割賦とは

自社割賦とは、商品やサービスを販売する際に、第三者を介さずに顧客と分割払いの契約を結ぶ販売方式です。クレジットカードのように信販会社などが間に入るのではなく、顧客との二者間契約であることが重要なポイントです。
自社割賦は「割賦販売法」の第2条1項の「割賦販売」に該当します。割賦販売法では割賦販売の定義を「2か月以上の期間」かつ「3回以上に分割して受領する」としています。
自社割賦は柔軟性が高くメリットの多い販売方法ですが、同時に金融事業としてのリスクが発生します。
自社割賦を導入しようと検討している企業は、メリットとデメリットを把握して、自社にとってプラスになるか判断してください。
自社割賦を導入するメリット

自社メリットを導入すると、柔軟な審査が可能となり、新たに手数料収入も見込めます。
ここでは、自社割賦を導入するメリットを解説します。
柔軟な審査が可能になる
自社割賦を導入すると、柔軟な審査が可能となります。
外部の信販会社を利用すると、自社では審査内容に口出しができませんが、自社割賦であれば自社で審査内容を決められるためです。
自社の取引履歴や顧客データ、AIなどを活用して審査をすれば、最適な与信基準となり審査を通過できる顧客が増える可能性があります。
手数料収入を見込める
割賦販売をする際は、手数料や利息などを請求するのが一般的です。
商品やサービスの販売以外に、手数料や利息などの収益を確保できるのも自社割賦のメリットです。
手数料や利息は自社で設定が可能です。商品の原価や市場競争力などの要因を加味しながら、トータルでの利益率を戦略的にコントロールできるでしょう。
新たな客層を取り込める
支払方法の選択肢が広がると、顧客が商品やサービスを購入しやすくなります。
その結果、これまで自社の商品やサービスを購入していなかった客層を取り込めるでしょう。
また、自社割賦を運用すると、顧客の支払い行動や信用履歴などの情報が社内に蓄積されます。
このデータを分析することにより、マーケティングやリスク管理が可能です。力を入れるべき客層や、避けるべき客層をより正確に判断できるでしょう。
自社割賦を導入するデメリット

自社割賦を導入すると、督促業務や債権管理の手間が増えてしまいます。
ここでは、自社割賦を導入するデメリットを解説します。
督促業務や債権管理の業務が増える
自社割賦はメリットの多い販売方式ですが、以下のような業務が増えてしまいます。
- 請求処理
- 入金確認
- 延滞者に対する督促 など
これらの業務は、本業である商品やサービスの販売のノウハウとは大きく異なります。何も対策を取らずに自社割賦を導入すると、業務に大きな負担がかかるでしょう。
債権管理に関する業務負担を減らすには、SOMOが提供する「分割PAY」のような専門的なシステムの導入が必要です。
債権管理のようなノンコア業務にリソースを割くと、本業である商品やサービスの販売に影響が出る可能性があります。機会損失をしないためにも、自社割賦を導入する際は業務の負担軽減策も一緒に検討しましょう。
未回収が発生するリスクがある
自社割賦は、購入者との二者での契約のため、未回収が発生すると貸倒損失を全額負担しなければなりません。
未回収が短期間に複数回発生すると、短期的な資金繰りがひっ迫して、経営に大きな影響を与える可能性があります。
また、貸倒れの金額が大きくなると、金融機関からの融資審査において、企業の信用を低下させる容認となります。融資を受ける予定がある場合は、未回収のリスクを減らす施策を取ったうえで、自社割賦を導入してください。
自社割賦と包括信用購入あっせんの違い
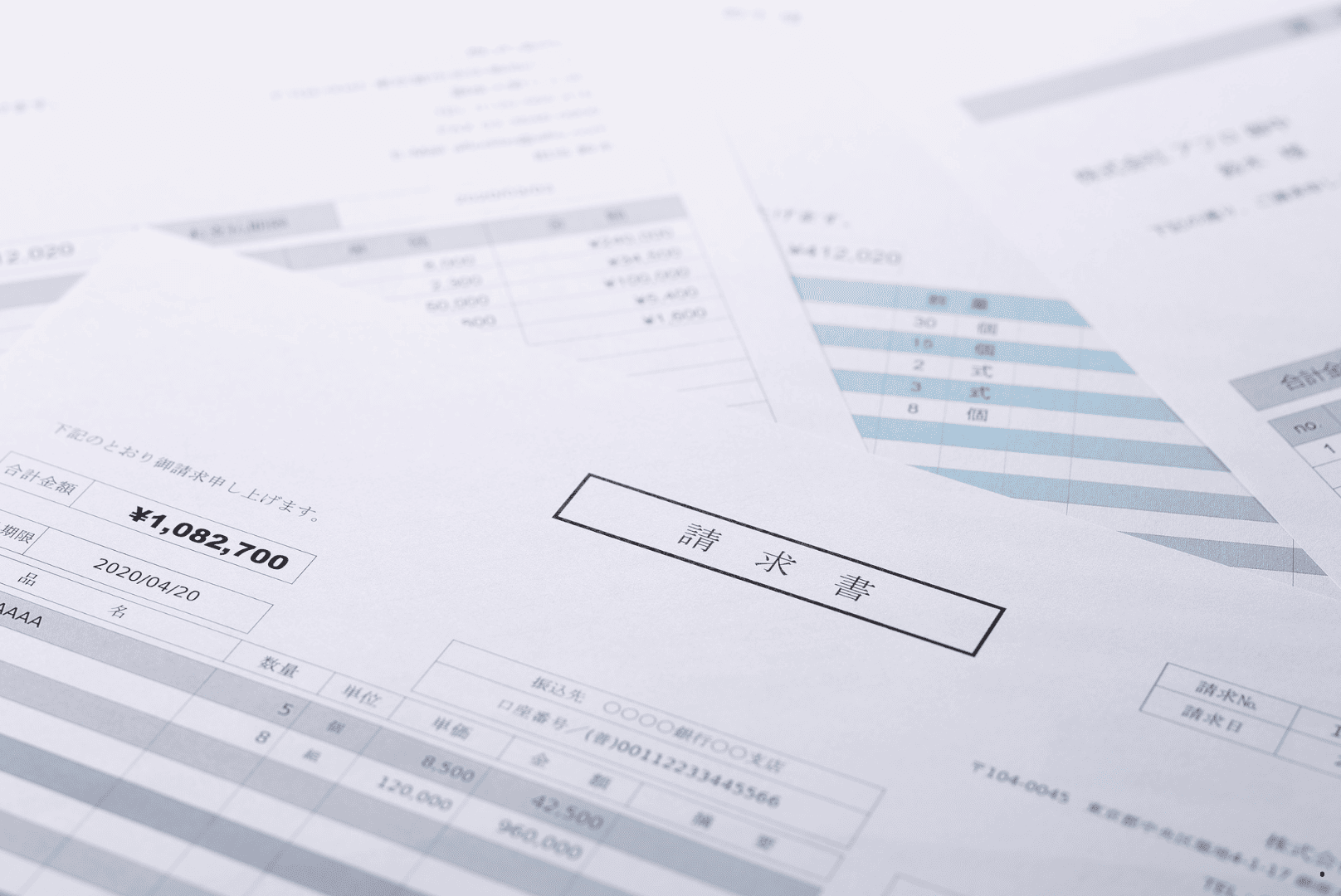
自社割賦の導入を検討する際は、包括信用購入あっせんについても把握しておきましょう。
包括信用購入あっせんとは、クレジットカード会社などの信販会社が商品の代金を立て替えて、顧客が信販会社に分割払いする販売方法です。
販売企業に代金の回収や督促業務は発生せず、未回収のリスクもありません。
ただ、審査やリスク管理も信販会社がおこなうため、顧客のデータを直接管理できず、マーケティングに活用できません。
自社割賦と包括信用購入あっせんの違いを表にまとめました。
| 自社割賦 | 包括信用購入あっせん | |
| 法的分類 | 割賦販売法上の「割賦販売」 | 割賦販売法上の「包括信用購入あっせん」 |
| 債権者 | 商品・サービスを提供する企業(自社) | クレジット会社(第三者) |
| 回収リスク | 企業(自社)が全リスクを負担 | クレジット会社が負担 |
| 審査の柔軟性 | 高い(自社基準に基づく) | 低い(外部機関の信用情報に基づく) |
| 運用負荷 | 高い(債権管理・督促業務の内製化) | 低い(提携手数料のみ) |
自社割賦の注意点
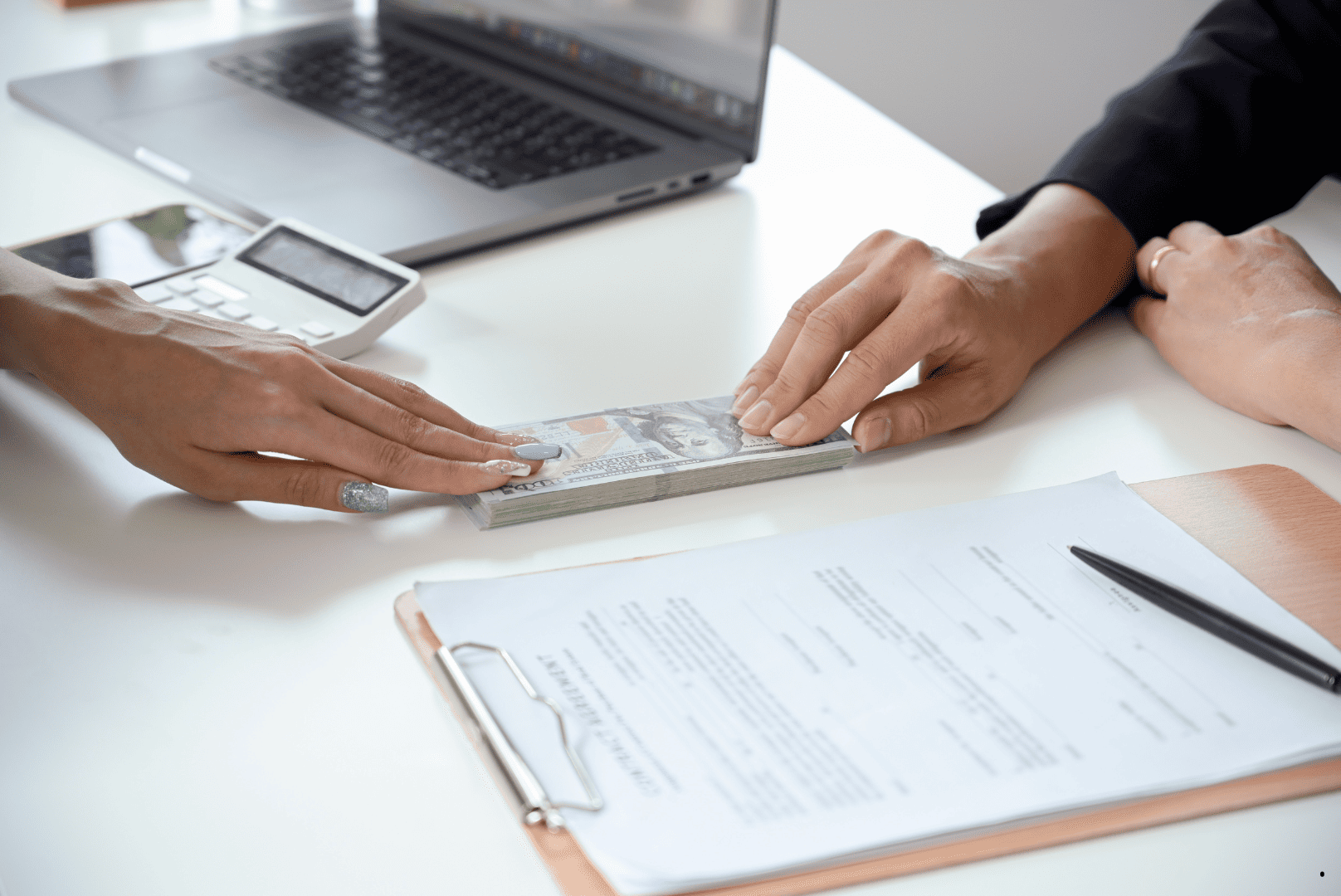
自社割賦を提供する際は、割賦販売条件の表示や契約書面の交付などをする必要があります。
ここでは、自社割賦の注意点を解説します。
割賦販売条件の表示
自社割賦は、割賦販売法第3条に基づき、契約内容の透明性を確保するために、以下のような正確な情報を表示する義務があります。
- 現金販売価格
- 割賦販売価格
- 割賦手数料の実質年率
- 支払期間および支払い回数
- 支払金額及び支払い時期
- 所有権留保の有無
これらの情報が表示をされていなかったり、誤解を招く記載があったりした場合は、割賦販売法違反として行政処分を受ける可能性があります。
契約書面の交付
割賦販売契約の締結後は、割賦販売法第4条に基づき、遅滞なく契約書面を交付する必要があります。
契約書面には、割賦販売の条件に加えて、契約解除の条件や顧客の抗弁権に関する事項など、定められた内容を記載してください。
近年では電子商取引が増えているため、顧客の承諾を得て電子データで契約書面を交付するケースも増えています。
自社割賦を導入するには、システムを設計する段階から法律的な要件を盛り込みましょう。また、法律が改正された際には、すぐに対応する必要があります。
まとめ
自社割賦とは、商品やサービスを販売する際に、他者を介さず自社と購入者で割賦販売契約を結ぶ販売方法です。
自社割賦を導入すると、柔軟な審査が可能になるだけでなく、手数料や利息などの新たな収入が見込めます。また、販売方法が増えることにより、新たな客層の取り込みも狙えるでしょう。
一方で、督促業務や債権管理業務の手間が増える・未回収が発生するなどのリスクもあります。
自社割賦を導入する際は、債権管理業務の効率化や未回収発生時の対応・包括信用購入あっせんとの違いなども考慮してください。
SOMOでは、自社で分割払い決済を提供するためのクラウドサービス「分割PAY」を運営しています。分割払いの提供でお悩み事がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
